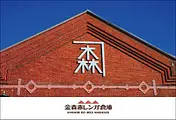旧日本銀行函館支店(函館市北方民族資料館)



上方に旧函館区公会堂が建つ基坂の麓に、まるで冷静に街を凝視しているかのような表情をした、コンクリート造りの建物があります。函館市北方民族資料館。かつての日本銀行函館支店です。明治時代後期から昭和初期にかけて、函館の金融街は末広町にありました。現在の電車通りに多くの銀行が建てられ、他のビルと連なる街並は、都会特有のオフィス・商業施設集合地域そのものでした。
これは、1926年(大正15年)に竹中工務店(推測)によって建てられたものです。ちょうど2年前の大正13年に、あたり一帯の建物を消失させた大火があり、次々と鉄筋コンクリート建築物が新築された時期であり、凝ったデザインのものも競い合うように多かったのですが、なぜか日本銀行だけは、ご覧のように無機質な印象を受けるものでした。
そこで、この場所に建てられてきた日本銀行の建物の変遷を見てみましょう。写真として確認できる最初の日銀は、明治44年築の木造2階建てのもの(写真はこちら)。何と、この建物は明治の建築界の巨匠、辰野金吾と弟子の長野宇平治の設計であったのです。辰野金吾といえば、東京駅や日本銀行本店などを手掛けた大物であります。
その後、前述のように火事によって消失したため、代わりに建てられたものを見ると、現在とは違って、角以外の2階の窓の枠取りがアーチ状になっていたり、電車通り側は円柱、基坂側は角柱と、面によって使い分けされたり。「何だ、けっこう粋じゃないか」と思われるデザインです。
それが現在の姿になったのは、昭和30年代に大規模な増改築を実施した際の外観変更のためであります。だから、新築当時の姿をイメージしながら資料館の玄関ホールや広間などを眺めると、納得できるはず。当時の函館の建築界は、やはり期待通りの意匠をきちんと用意していたのです。
どうぞ、明治、大正、昭和とそれぞれが異なった姿であった日本銀行のイメージを比べながら、実際に建物の壁に手を触れ、時代の変化を体感してみてください。
参考資料/関根要太郎@はこだて
関連記事
函館市北方民族資料館
カテゴリー
-
ベイエリア
-
歴史的建造物(一般入場可)
-
街歩き
-
明治・大正の建物
-
歴史好きに
-
博物館・資料館等
-
雨や雪でも楽しめる
-
市電から徒歩5分以内
-
車イス対応トイレ
-
オムツ替えスペース
-
英語看板
詳細情報
| 住所 | 函館市末広町21-7 |
|---|---|
| アクセス情報 |
市電 「末広町」電停 下車 徒歩1分 |
| 電話番号 | 0138-22-4128 |
| 利用時間 |
9:00~19:00(4~10月)、9:00~17:00(11~3月) |
| 休日 |
12月31日~1月3日、器材点検日、随時 |
| 利用料金 |
一般300円、学生・生徒・児童150円。共通券あり |
| 駐車場 |
なし(元町観光駐車場など) |
| 関連リンク |
函館市北方民族資料館(函館市文化・スポーツ振興財団) |

.jpg)


















.jpg)