アーレンスフォックス号(ポンプ消防車)


函館市消防本部1階ロビーに入ると左手に展示されているのが、アメリカ製のクラシカルなポンプ消防車「アーレンスフォックス号」です。1919(大正8)年から1954(昭和29)年までの35年間、函館市内で実際に使われていて、国内に現存するポンプ消防車の中で最も古いもの。全国的にみても、東京消防庁が消防博物館で保存展示しているものとこれの2台しか現存しない、貴重な1台です。
函館では、度重なる大火の歴史のなかで、1894(明治22)年には上水道と地下式消火栓の整備が始まり、1913(大正2)年には非常用水道の設置を開始するなど、消防力の強化や近代化を図ってきました。1919(大正8)年には、時の消防組頭勝田弥吉氏が尽力し、函館区民から募った寄付金2万8000円(当時)をもとに、アメリカのアーレンスフォックス社製のポンプ自動車を導入、「アーレンスフォックス号」と名づけられました。ポンプ自動車の導入は東京より数年早く、最高時速は約100キロ、1分間に2850リットルの水を42メートル先まで放水できる優秀さから、導入当時は「未だかつて、全国にその類なし」と形容されたほど。車体前部に搭載されているポンプはガソリンエンジンで駆動するため、従来の蒸気ポンプよりも迅速に消火活動が開始できるようになりました。
現在の消防車のように運転席に屋根や扉はなく、二人掛けの座席が備わる程度で、後部の立ち席には8名の消防士が乗車できたとのこと。車体側面には川などから給水する際に使うホースや消火用のホースが備わり、タイヤもスポーク車輪と、クラシックなスタイルが特徴的です。
1921(大正10)年には函館の豪商・相馬哲平氏(初代)からの寄付5万円をもとに同型車が2台追加導入され、1台は「相馬号」と名づけられ、1934(昭和9)年3月21日に発生した函館大火の際にも活躍しました。これらの3台のうち1台は昭和9年の大火で焼失し、もう1台も廃車、最後の1台となったアーレンスフォックス号は、昭和29年に引退するまでの35年もの長きにわたって活躍しました。引退後も函館市の倉庫で保管され、市立函館博物館を経て、現在は函館市消防本部の1階ロビーで保存・展示されています。
ロビーには、昭和12年から函館市内各所に設置されている函館市独自の消火栓「函館型三方式地上式消火栓」と、それ以前から使われている地下式消火栓と立管の実物が展示されており、函館の消防の歴史を垣間見ることができます。
カテゴリー
-
函館駅前・大門
-
銅像・記念物
-
レトロ
-
歴史好きに
-
雨や雪でも楽しめる
-
市電から徒歩5分以内
-
車イス対応トイレ
詳細情報
| 住所 | 函館市東雲町5-9 |
|---|---|
| アクセス情報 |
市電 「市役所前」電停 下車 徒歩3分 |
| 問合せ先 | 函館市消防本部 |
| 電話番号 | 0138-22-2142 |
| 利用時間 |
8:45~17:30 |
| 休日 |
土日祝日 |
| 利用料金 |
入場無料 |
| 駐車場 |
周辺に有料駐車場あり |
| 関連リンク |
消防自動車「アーレンスフォックス」(函館市) 函館市消防本部 |

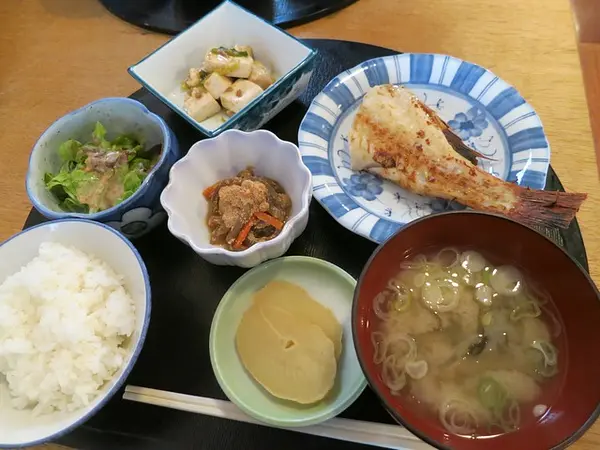

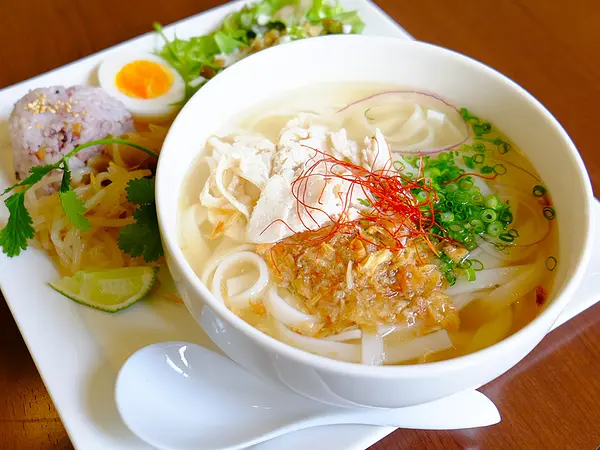












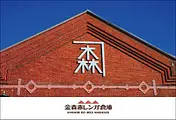













.jpg)
