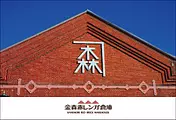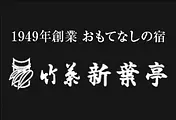松原家住宅
市電「大町」電停を降り、幅が広く比較的緩やかな弥生坂を上ると、バス通りとの交差点に至ります。そこで目を右手にやると、角から2軒目に切妻の大屋根が目立つ建物があります。それが松原家住宅(個人宅)です。
この建物は、1910(明治43)年に建築されたという記録があるそうです。1907(明治40)年の大火によってこのあたりの建物が焼失して間もない頃のことなので、素早い復興が可能だった当時の函館の経済力を知るうえで、貴重な建物のひとつといえます。明治後期から昭和初期まで、このあたりは歓楽街として栄えた地域でした。すぐ近くには巴見番(芸者の置屋)や料亭などがあり、財力のある海産商の旦那たちが芸者さんを呼んで料理屋で遊ぶ......という賑わいをみせていたようです。その一角に、当時のある海産商が建てたのがこの家でした。
建物は京都などにある町家風で、実際に建築時には京都から大工を呼んだとの話もあります。壁は柱を見せる「真壁」で、開口部には格子が施されているなど、江戸時代から続く和の意匠を継承したものとなっています。また、庇部分に化粧垂木を施し、とても平家とは思えない高く重い瓦を載せた屋根をしっかり支えており、側面の壁には簓子(ささらご)下見張りを採用するなど、建築費も相当要したのではないかと想像されます。その堅固な造りによって、築100年以上経った今でも、その凛として静かに佇む姿を私たちに見せてくれているわけです。
この松原邸では、正月になると屋号の入った大きな暖簾が玄関先に飾られます。建物だけではなく、私たちがほっとする風情と伝統を保っていることに、洋風化が進む現代でも忘れてはならない和の心を思い出さずにはいられません。
明治時代の繁栄の中心地であったこの周辺の面影を残している、貴重な建物。明治時代からほとんど変わっていない、松原邸がある通りとこの建物を眺め、芸者さんたちや粋な衣装を纏った旦那衆が歩いているシーンを想像してみてください。そうすれば、このような奥ゆかしい建物がここにあるのが、全く自然であることと思えるでしょう。
なお、私有物のため、公道からの見学になります。
なお、私有物のため、公道からの見学になります。
参考資料/函館市史
カテゴリー
-
ベイエリア
-
歴史的建造物(外観は見学可)
-
街歩き
-
明治・大正の建物
-
歴史好きに
-
指定文化財等
-
市電から徒歩5分以内
詳細情報
| 住所 | 函館市大町5-2 |
|---|---|
| アクセス情報 |
市電 「大町」電停 下車 徒歩3分 |
| 問合せ先 | 函館市観光案内所 |
| 電話番号 | 0138-23-5440 |
| 利用時間 |
外観のみ見学可 |
| 駐車場 |
周辺に有料駐車場あり |