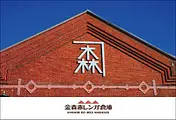天祐寺



天祐寺は青柳町にある天台宗の寺で、1850(嘉永3)年、福島県相馬から来た僧が大聖歓喜天(だいしょうかんぎてん)を祀ったのがはじまり。江戸末期、様似・等澍院の箱館休泊所となった際に天祐庵と称され、1884(明治17)年に現在の名前に改められました。1934(昭和9)年の函館大火の時に寺は全焼しましたが、2年後、東京にあった紀州徳川家の江戸屋敷を移築し、書院として建てられました。
大聖歓喜天は別堂に祀られており、寺の前の青柳坂は「聖天坂(しょうでんざか)」とも呼ばれていました。1954(昭和29)年の台風で本堂が倒れ、その後の再建工事の際には縄文中後期時代の貝塚も発見されて土器が出土し、「天祐寺貝塚」と名づけられたという歴史も残っています。
本堂に向かって右前には、薬師如来石像が祀られています。こちらはかつて函館山にあったもので、明治時代に土中に埋められ、のちに函館山が要塞地帯となって兵隊によって掘り出され、要塞司令部そばに安置されていましたが、一般の人にも広く信仰されるようにと、寺に奉納されたものです。また、境内には、函館山七福神の一柱で、開運隆盛の福神として知られている布袋尊も祀られています。
大聖歓喜天は長い鼻をもつ象頭人身の像で、その象牙を大根に見立てて奉納していることから、毎年9月には、直径1メートルの大鍋で煮た大根鍋のふるまいや余興などが行われる「大根祭」が開催されており、地域住民に親しまれています。
カテゴリー
-
元町・函館山
-
神社・寺
-
明治・大正の建物
-
神社仏閣
-
市電から徒歩5分以内
-
無料駐車場
詳細情報
| 住所 | 函館市青柳町27-26 |
|---|---|
| アクセス情報 |
市電 「宝来町」電停 下車 徒歩5分 |
| 電話番号 | 0138-22-0483 |
| 駐車場 |
無料駐車場あり |










.jpg)