函館漁港 船入澗防波堤


市電「函館どつく前」電停から徒歩5分ほどの函館漁港(入舟漁港)にあるのが、船入澗防波堤です。1896(明治29)年から始まった港湾改良工事の折に造られたもので、石材は、工事に先立って解体・埋め立てられた弁天台場の間知石や亀腹石を転用したものです。
この防波堤の設計を手掛けたのは、近代土木の父として著名な、札幌農学校(現在の北海道大学)の広井勇博士。弁天台場を解体する折に、「此建築は今日のものに比して毫(ごう)も劣る所なし」と嘆じたほど、その堅牢さは特筆すべきものでした。防波堤の設計には弁天台場の技術も生かされているほか、当時の最新技術であったコンクリートブロックも併用されています。
完成から100年以上使われつづけ、石組みがずれるなどの老朽化が進んでいましたが、2004(平成16)年度の土木学会選奨土木遺産に選定されたことをきっかけに、2013(平成25)年に石積みや欠損個所の修復工事が行われ、現在でも現役の防波堤として活躍しています。傍らにある函館港改良工事記念碑も、弁天台場の石材を流用したものです。
なお、現役の港湾施設であるので、足元には段差や突起物、ロープやワイヤーなどがあるほか、最近の堤防よりも幅が狭いため、充分な注意が必要です。
古写真:函館市中央図書館所蔵
この防波堤の設計を手掛けたのは、近代土木の父として著名な、札幌農学校(現在の北海道大学)の広井勇博士。弁天台場を解体する折に、「此建築は今日のものに比して毫(ごう)も劣る所なし」と嘆じたほど、その堅牢さは特筆すべきものでした。防波堤の設計には弁天台場の技術も生かされているほか、当時の最新技術であったコンクリートブロックも併用されています。
完成から100年以上使われつづけ、石組みがずれるなどの老朽化が進んでいましたが、2004(平成16)年度の土木学会選奨土木遺産に選定されたことをきっかけに、2013(平成25)年に石積みや欠損個所の修復工事が行われ、現在でも現役の防波堤として活躍しています。傍らにある函館港改良工事記念碑も、弁天台場の石材を流用したものです。
なお、現役の港湾施設であるので、足元には段差や突起物、ロープやワイヤーなどがあるほか、最近の堤防よりも幅が狭いため、充分な注意が必要です。
古写真:函館市中央図書館所蔵
カテゴリー
-
元町・函館山
-
歴史的建造物(外観は見学可)
-
景色(市内)
-
眺望がいい
-
歴史好きに
-
港・海
-
市電から徒歩5分以内
詳細情報
| 住所 | 函館市入舟町4-4 |
|---|---|
| アクセス情報 |
市電 「函館どつく前」電停 下車 徒歩5分 |
| 問合せ先 | 函館市観光案内所 |
| 電話番号 | 0138-23-5440 |
| 駐車場 |
周辺に有料駐車場あり |
| 関連リンク |
土木遺産 函館漁港 船入澗防波堤(国土交通省北海道開発局 函館開発建設部) 函館港改良施設群(土木学会選奨土木遺産) |













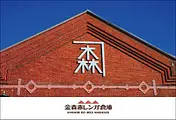












.jpg)

